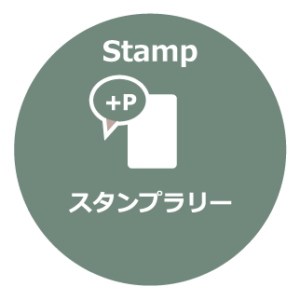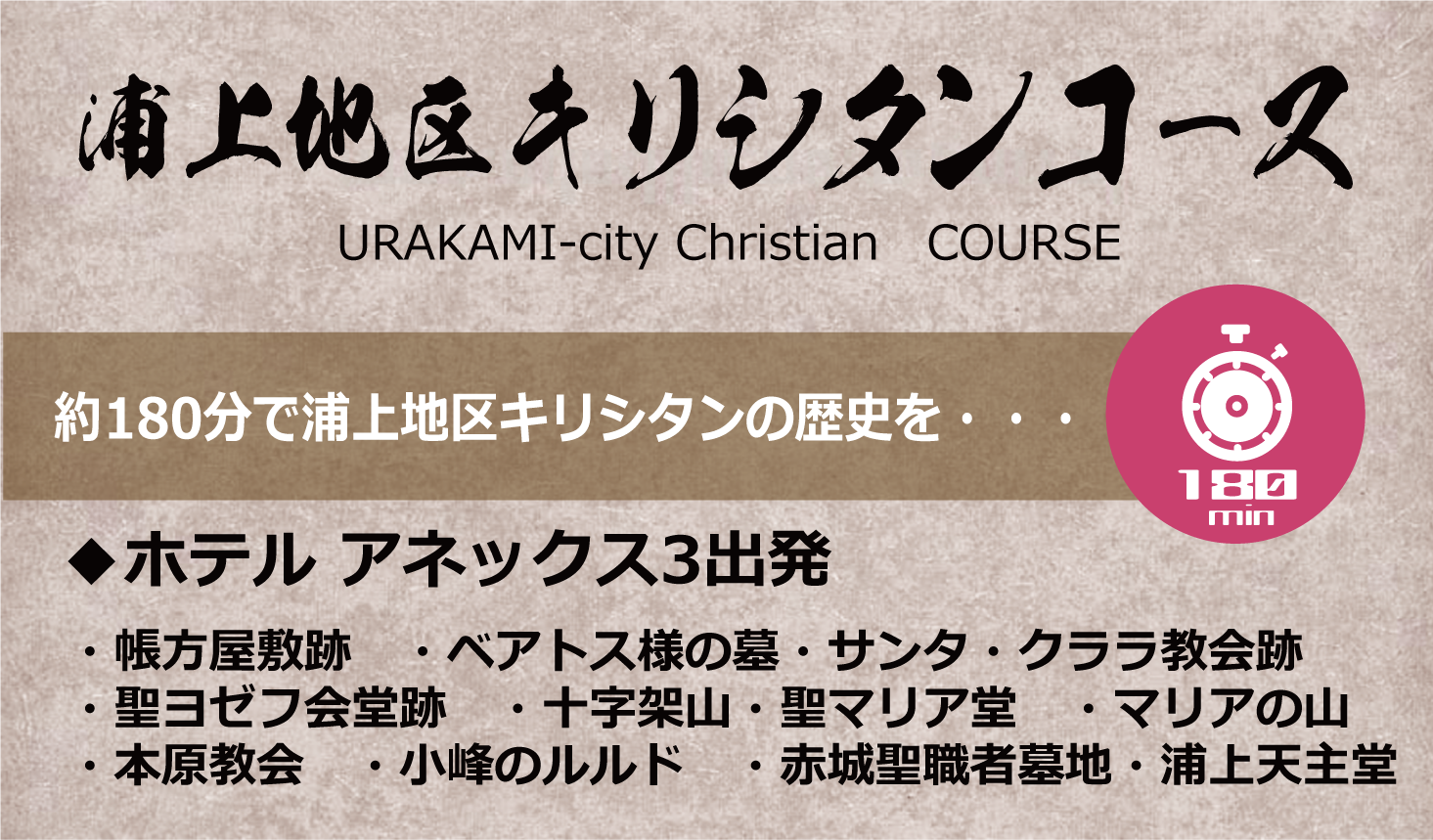潜伏キリシタンとは
1549年、イエズス会宣教師であるフランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した。ザビエルは、日本に初めてキリスト教を伝えた。その後、ザビエルの後継者であるコスメ・デ・トレス、バルタザル・ガーゴ、ルイス・フロイスらによって、キリスト教は、九州や西日本を中心に広がった。1563年には、大村純忠が洗礼を受け、日本最初のキリシタン大名となり、71年には南蛮貿易地として長崎港が開港され、大村純忠は1580年イエズス会に長崎六町を寄進し、長崎の新しい六町は教会領となった。
1587年伴天連追放令を発した豊臣秀吉はこれを没収し、天領とした。キリシタンの存在を警戒した江戸幕府は、1614年にキリスト教禁教令を発し、日本からキリスト教を全面的に禁止した。教会の破壊や宣教師の捕縛が行われた。天領長崎には長崎奉行が置かれ、長崎奉行は、一般信者を含めて徹底的な取り締まりを行い、絵踏みや、懸賞訴人制、五人組制度、寺受け制度、宗門人別改制度などが行われた。こうして長崎の中心部からキリシタンは姿を消した。
1644年頃、禁教の徹底でキリシタンはいなくなったと考えられたが、浦上村山里のキリシタンを中止に帳方、水方、聞役の三役の組織をつくって信仰を守り続けた。この人々を「潜伏キリシタン」を呼ぶ。帳方は、組織のリーダーであり、祝日の日取りを決める「御帳」を管理しオラショ(祈り)を伝承する役であった。水方は、洗礼を授ける役であった。聞役は、水方の助手で、触役とも呼ばれた。信心の道具として用いた観音像を「マリア観音」という。七代250年親から子へとオラショ(祈り)を唱え、洗礼を授けてきた。
1865年には浦上のキリシタンは完成したばかりのフランス寺(大浦天主堂)のプティジャン神父に同じ信仰をもつことを表明した。これが「信徒発見」の出来事である。しかし、キリスト教に対しての禁止はその後も続き、正式に禁が解かれたのは1873年になってからである。
現在は禁教時代のキリスト教信仰者を「潜伏キリシタン」、禁教解除後にもキリスト教とは異なる形の信仰を続ける人々を「かくれキリシタン」と区別するようになった。